UNSTANDARD
NONDESIGN
加盟の方はこちら
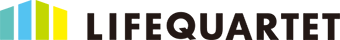

2025.11.21

INDEX

2025年、住宅業界は制度変更と市場環境の激変という二重の試練に直面した。工務店・ビルダー経営層、設計・現場責任者が押さえるべき重要な動向を5つのトレンドに整理する。
トレンド1:新設着工の大幅減少が継続
2025年7月の新設住宅着工戸数は前年同月比−9.7%と大幅なマイナスを記録。特に持家は−11.1%と二桁減となり、反動減の影響が色濃く出ている。
トレンド2:制度変更による業務負荷の急増
4月からの省エネ基準適合義務化と4号特例の縮小により、申請業務や設計作業の負荷が大幅に増加。審査期間の長期化も相まって、着工までのリードタイムに深刻な影響を与えている。
トレンド3:建設コストの高止まり継続
2015年平均を100とした建設資材物価指数(東京)は2025年8月時点で143.2と高水準を維持。前年同月比+3.2%の上昇を記録し、コスト圧迫が経営を直撃している。
トレンド4:人手不足の構造的深刻
2025年4月時点での建設業における正社員不足率は68.9%。職人不足に加え、新制度に対応可能な技術者の確保が急務である。
トレンド5:金利環境の微増傾向
フラット35の最頻金利は2025年10月時点で年1.89%。低金利は維持されているものの、微増傾向が顧客の購入判断に影響を与え始めている。
これら5つのトレンドについて、市場データと現場の実態を踏まえて詳しく見ていこう。
国土交通省が発表した建築着工統計は、業界の厳しい現実を浮き彫りにした。2025年7月の新設住宅着工戸数は前年同月比−9.7%と大幅な減少を記録。持家・貸家・分譲住宅が減少し、住宅市場の冷え込みが顕著である。
この背景には複合的な要因が存在する。第一に、省エネ義務化前の駆け込み需要の反動減。2025年3月までの駆け込み着工が相次いだ反動で、4月以降の着工が大幅に減少したのだ。
しかし、単純な反動減だけでは説明できない要素もある。建築費の高騰や制度変更による不透明感が、生活者の住宅購入判断を慎重化させているのだ。特に、省エネ基準適合による追加コストへの懸念や、新制度下での建築期間の長期化リスクが、購入決定の先送りを促している。
工務店やビルダーからは「契約は取れても着工まで時間がかかる」「顧客が様子見の姿勢を強めている」といった声が聞かれる。市場の底堅さは維持されているものの、短期的な需要の落ち込みは避けられない状況である。
2025年4月に施行された制度変更は、住宅業界の業務プロセスを根本的に変えている。最も大きな変化は、原則すべての住宅・建築物での省エネ基準適合義務化である。これまで説明義務に留まっていた小規模住宅についても、省エネ計算書の提出や基準クリアが必須となった。
同時に実施された4号特例の縮小も深刻な影響を与えている。従来は構造計算や審査が省略されていた木造2階建て住宅や延べ面積200㎡超の平屋についても、構造関係規定等の審査対象となり、提出図書の質・量が大幅に増加している。
これらの制度変更により、設計事務所や工務店の業務負荷は急激に増大。省エネ計算に不慣れな小規模事業者では、外部委託費の増加や対応スタッフの確保が経営課題となっている。
また、通常7日程度だった建築確認申請の審査期間は、最大35日へと延長。申請から着工までのリードタイムの長期化が各地で報告されており、着工スケジュールの管理が従来以上に困難になっている。

住宅業界の収益を圧迫し続けているのが、建設コストの高止まりだ。2015年の水準を100とした建設資材物価指数(東京)は2025年8月時点で143.2を記録し、前月比+0.1ポイント、前年同月比+3.2%の上昇となっている。
この背景には、原材料価格の上昇に加え、物流コストや人件費の継続的な上昇がある。特に木材については国際市況の影響を受けやすく、為替変動や海外需要の動向が直接的に建築費に影響している。
コスト上昇への対応については、企業規模や地域特性により状況が異なっている。建築主への価格転嫁が困難な事業者では利益率の圧迫が深刻化しており、同じ仕様の住宅でも収益性に差が生じている状況が見られる。
人手不足問題はより深刻度を増している。帝国データバンクの2025年4月調査によると、建設業における正社員不足率は68.9%。2024年問題から1年経過し、人手不足による影響が大きくなっている。
特に問題となっているのは、新制度に対応できる技術者の不足である。省エネ計算や構造計算ができる設計者、現場での省エネ施工を指導できる監理技術者の確保が急務。大手企業による技術者の引き抜きも激化しており、中小工務店では人材流出への対策が経営の最重要課題となっている。
職人不足についても状況は変わらず深刻である。これにより工期の延長や品質のばらつきが発生し、顧客満足度の低下リスクが高まっている。
また、熟練職人の高齢化と若手職人の不足により、技能継承も大きな課題だ。建設業界全体の魅力向上と働き方改革が急務である。
住宅ローン金利については、依然として歴史的低水準を維持しているものの、微増傾向が見られる。フラット35の最頻金利は10月時点で1.89%となっており、若干の上昇が確認できる。
この微増は購入検討者の心理に微妙な影響を与えている。「今が買い時」という切迫感が薄れる一方で、「もう少し様子を見よう」という慎重姿勢を後押ししている側面がある。特に借入額の大きい高額物件では、月々の返済額への影響が無視できないレベルとなっている。
2025年度は「子育てエコホーム支援事業」の新築住宅への補助については一定の効果を上げているものの、予算の執行状況と申請期限の管理には注意が必要だ。予算枠の早期消化が予想されるため、対象案件については早期の申請準備が重要となっている。
また、省エネ基準適合義務化との相乗効果により、高性能住宅への誘導は一定程度進んでいるものの、コスト増加分を完全にカバーするには至っておらず、事業者の負担増加は避けられない状況である。

2025年度の住宅業界は、今回紹介したトレンドが示すように、制度変更による混乱と市場環境の悪化に見舞われた困難な時期であった。新設着工戸数の減少、建設コストの高止まり、深刻な人手不足という三重苦に加え、省エネ基準適合義務化と4号特例縮小による業務負荷の急増が業界全体を直撃した。
しかし、この試練は同時に業界の構造改革を促進する契機でもある。制度変更への対応を通じて、技術力向上と業務効率化が進展。また、高性能住宅への需要喚起により、付加価値の高い商品への転換も進んでいる。
今後の課題は明確だ。第一に、新制度下での安定的な供給体制の構築。第二に、コスト上昇圧力への対応と収益性の確保。第三に、人材確保と技術者の育成。これらの課題に適切に対応できる企業が、次の成長ステージでの勝者となるであろう。